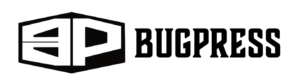センゼ畑と伝統野菜
鵜飼照喜 (信州大学名誉教授 環境社会学)
伝統野菜
この頃、地域創生とか地域振興という掛け声の下で、「地域の伝統野菜」がクローズアップされてきている傾向がみられる。ここでいう伝統野菜とは長野県小布施町のまる茄子のような事例をいうのであろう。また、伝統というのは「今日的な品種改良」によらないという意味であろう。したがって、当該地域で小規模生産ながら脈々と栽培されてきたことを指していると考えられる。
他方で、同じ茄子の仲間ではあるが、一定の気象条件などが適している全国各地で大規模生産され、大量に全国規模で流通している茄子類があり、茄子以外の多くの野菜でも同様である。
そうした野菜類は伝統野菜とは言われないが、最近は農産物に限らず商品には産地表示が求められているので、どこのスーパーでも商品の産地がどこであるかは、消費者にはすぐわかるようになっている。そのせいか、スーパー等での買い物の際には、いつの間にか産地を確認する癖がついてしまっている。
ところで、こうした「伝統野菜」とそうでない野菜たちとの相違は、どこに由来するのであろうか?

農業基基本法(1961年制定)の役割
「伝統野菜」とは言われない野菜たちは、1961年に制定された農業基本法の下で政策展開された「主産地形成」政策にのっとり大規模生産・大量流通にしたがって大量消費されるという政策の流れにうまく乗った「品種」ではないかと考えられる。逆に、そうした流れに乗らなかった「品種」が「伝統野菜」といわれるようになったと考えられる。
このように考えれば、茄子に限らず、ある農産物について主産地形成政策の流れに乗った「品種」とそうでない品種の相違が、いわば政策的に作り出されたといえる。少し厳しい言い方をすれば「伝統野菜」は、いわば農業基本法に基づく「主産地形成」政策から取り残された品種ということができる。「取り残された」という表現が不適切というならば、マイナーな品種とでも言おうか。
では、まる茄子のようなマイナーな品種は、なぜ取り残されたか、という点については大量生産・大量流通に不向きである等栽培技術のむつかしさか、あるいは「政策決定」に携わるところまで認知されていなかったという社会的事情などが考えられる。
しかしながら、こうしたマイナーな品種の野菜たちが、今日改めて「伝統野菜」として日の目を見るようになったことは、喜ばしい傾向であるといえよう。そして、その伝統野菜を継承してきた農家の人たちに敬意を表したいと思う。
ところで、平成18年9月には、長野県で信州伝統野菜認定制度が始まった。その制度について長野県ホームページでは次のように説明されている。
『長野県内で栽培されている野菜のうち、「来歴」「食文化」「品種特性」という3項目について、一定の基準を満たしたものを「信州の伝統野菜」として選定しています。選定された「信州の伝統野菜」のうち、伝承地で継続的に栽培されている伝統野菜および一定の基準を満たした生産者グループ(生産者組織、農協、市町村等)に対して、「伝承地栽培認定」を行っています。伝承地栽培認定を受けた生産者グループは、「信州の伝統野菜認定証票」(認定マーク)を表示して出荷・販売することができます。』
ここに見られるように、生産者に関しては、個人ではなく、生産者グループを対象とした制度となっており、かつての主産地形成とは異なる「伝統野菜産地形成」ともいうべき、農業振興政策としての位置づけがあるということができる。
センゼ畑
それでは、表題の「センゼ畑」とは何か?また「伝統野菜」とどう結びつくのか?
前述のように、今日「伝統野菜」といわれる野菜類は、大量生産・大量消費という高度経済成長の流れの中で、いくつかの野菜たちの中のマイナーな品種である。したがって、小規模生産・小規模消費という特色を持つ。その最小規模は自給自足規模である。あるいは、地域内での流通としても、せいぜいご近所か、都会で生活している子供たちへ送る程度である。最大で「各地の道の駅」で販売される程度であろう。マイナーな野菜たちがその地域を超えて、「伝統野菜」として認知されるようになったのは、おそらく道の駅の役割が大きいと考えられる。
道の駅での販売が「伝統野菜」の存在を旅行者たちにより、「全国化」し、「市場商品化」したのであろう。この全国化・市場商品化の過程は、伝統野菜の栽培規模拡大をもたらす効果を持っている。
しかし、いまだ「伝統野菜」として「認知」される以前は、農家の「商品作物」用の耕地で栽培されることはない。それゆえ、「農業経営」の枠には組み込まれていない自給用作物である。自給用であるから、その栽培の担い手の多くは農家の主婦・農家の食事を担う女性たちである。まれに、現役を引退した農家の男性という事例を聞いたこともある。
その栽培用の畑は、自給用の小規模で、家屋に近いところに位置することが多い。それを「せんぜ畑」という。この言葉は、長野県北部で比較的よくつかわれる言葉であり、所によっては「せんざい畑」ともいう。全国的にも類似した言葉で使われていると考えられる。
名義上、耕地の所有者は一般的には農家の世帯主=男性であろうが、せんぜ畑の主は、名実ともに農家の女性たちである。小布施町では、現役を退いた男性が使っているという事例もあるという。
では、「せんぜ」、あるいは「ぜんざい」とは何か?また、その言葉の由来は何か?
これは私が学生時代に、農村社会学で農村調査をされていた恩師の一人から聞いたことである。おそらく柳田民俗学に由来すると考えられるが、漢字では「前栽」と書く。「前栽」とは貴族の屋敷内の一角に「自家用」の作物を栽培することを意味する。もとより、その一角とは屋敷内の北側の日陰ではなく、家屋の南側の日のよく当たるところであろう。当然屋敷の主からすれば、家屋の南側は丁寧に手入れされた庭の片隅であろうが、庭を愛でる位置からは目の「前」である。
こうして「せんぜ畑」は、貴族の屋敷内の自家用栽培から生まれた言葉である。貴族というからには、時代は平安時代、しかし必ずしも豊かではない貴族たちの生活の「自家用の畑」である。「せんぜ畑」で従事するのは、おそらく使用人が大半であろうが、屋敷の主である貴族の男や女たちはどんな思いでその作業を見ていたのであろうか?
日本人の主食といわれるコメについては、全国各地で品種改良が進みいわゆる「銘柄米」が多数生み出されている点では、コメの中で「伝統米」といわれる品種には、お目にかかったことがない。この点では、コメは特別扱いされてきたといえるのでないか。
鵜飼照喜著「沖縄 巨大開発の論理と批判」(社会評論社刊)
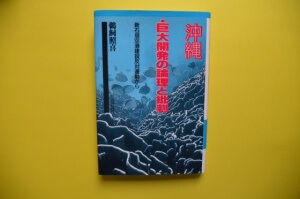
日本で環境社会学学会が設立された年(1992年)に著された鵜飼照喜氏による空港建設を環境社会学的視点から見た著書。